【 解説 】 ※ 画像クリック拡大表示


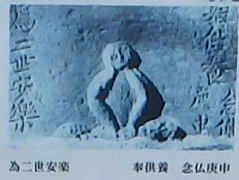 〔 地蔵尊のご案内 〕 所在地:南成瀬 8-12
〔 地蔵尊のご案内 〕 所在地:南成瀬 8-12
地蔵菩薩立像・丸彫り一猿・像高 148cm
( ※ 案内板の拡大写真を撮影し忘れた )
「一猿」とは、地蔵菩薩像の台座正面(中央の写真)に彫られた猿の像(右の写真)と思われる


 〔 馬頭観音(ばとうかんのん) 〕 馬頭観音は観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)が六変化(ろくへんげ)し、その内の一つが馬頭観音となって天界(てんかい)・人界(じんかい)・地獄(じごく)・餓鬼(がき)・畜生(ちくしょう)・修羅(しゅら)の世界を生まれ変わり、死に変わりして永久に苦しむ人間を、仏(ほとけ)の道によって救いこの世の苦海(くかい)を渡らせ、極楽(ごくらく)に至らせると言われています。それらの考え方が馬を扱って生活する農民や商人たちの信仰を集めてやがて馬の無病息災祈願(むびょうそくさいきがん)から、馬の墓標や供養塔に転化(てんか)したものです。 平成28年(2016)正月 東光寺講中(こうじゅう) 〔 馬頭観音(ばとうかんのん) 〕 馬頭観音は観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)が六変化(ろくへんげ)し、その内の一つが馬頭観音となって天界(てんかい)・人界(じんかい)・地獄(じごく)・餓鬼(がき)・畜生(ちくしょう)・修羅(しゅら)の世界を生まれ変わり、死に変わりして永久に苦しむ人間を、仏(ほとけ)の道によって救いこの世の苦海(くかい)を渡らせ、極楽(ごくらく)に至らせると言われています。それらの考え方が馬を扱って生活する農民や商人たちの信仰を集めてやがて馬の無病息災祈願(むびょうそくさいきがん)から、馬の墓標や供養塔に転化(てんか)したものです。 平成28年(2016)正月 東光寺講中(こうじゅう)

 〔 天狗童子立像(道祖神 どうそじん) 〕
〔 天狗童子立像(道祖神 どうそじん) 〕
舟形光背・H 490・W 310・L 140 / 建立・武蔵 成瀬東光寺村惣氏子
完全な形に近い天狗童子立像(鳥天狗)で全国的にも類例を見ないとされる貴重なものである。しかも成瀬には三体あって(山村・西ノ久保にも現存している)大きさは違うが、いずれも舟形の立像である。髪を高く結い、つり上がり気味の両眼を半眼に開いて翼を左右に拡げている、右手に七裂の八ツ手を持って胸に当て、左の手には錫杖(しゃくじょう)を握っている道祖神である。昔、中村に三間四方の薬師堂があり、此処を中心として修験者たちが祈祷を業としながら造塔信仰を広めていたと云われている、村人と修験者との深い関わりの中から生まれた天狗童子像の道祖神が村の守り神として建立されたものと推測されている。伝承文製作・平成23年(2011)11月・中里猪一
〔 地神塔(ちじんとう) 山型角塔 〕
大きさ=H 700・W 320・L 320 / 建立・武蔵 多摩郡成瀬村東光寺 嘉永2年(1849)2月
成瀬村の年表を見ると地神塔が立てられる4年前には大干ばつが起こり終日「村中で水番を行う」との記録がある。川の水を水田に取り入れるために寝ずの番をして、堰や畦道を監視し争いを避け、そして豊作を祈ったのであろう。この場所は柳谷戸を源流とする柳川(小川)が流れ、揚水するための「東光寺堰」の前であった、土地区画整理事業で川を移動させた堰跡附近で、かつては水田用水などの協議や作業の相談が行われた所である。不作が続き不安な生活が村人の心に「稲作の豊かな稔りを祈る思い」を膨らまさせ、それが地神塔を立てさせたものと思える。伝承文製作・平成23年(2011)11月・中里猪一
 〔 地神様(ちじんさま)の本尊石(ほんぞんいし) 〕 年中行事として毎年1月14日に催される『だんご焼き』(どんど焼き・せいと焼きなどと呼ぶところもあります)の火の中にこの石を入れておきます。本尊石の御利益(ごりやく)で、この火で焼いた「だんご」を食べると風邪など引かない元気な一年を過ごすことが出来ると言われております。「だんご焼き」の行事が終わると取り出して来年の出番まで地神様の横に安置され御利益を蓄えます。 〔 地神様(ちじんさま)の本尊石(ほんぞんいし) 〕 年中行事として毎年1月14日に催される『だんご焼き』(どんど焼き・せいと焼きなどと呼ぶところもあります)の火の中にこの石を入れておきます。本尊石の御利益(ごりやく)で、この火で焼いた「だんご」を食べると風邪など引かない元気な一年を過ごすことが出来ると言われております。「だんご焼き」の行事が終わると取り出して来年の出番まで地神様の横に安置され御利益を蓄えます。
平成28年(2016)正月 東光寺講中
 〔 第8号 成瀬 山吹(やまぶき)特別緑地保全地区 〕 名称の「山吹(やまぶき)」は、昔からの地名である「山村(やまむら)」と「吹上(ふきあげ)」の両方の場所にまたがることに由来しています。区域は、南北及び東側に伸びており、町田市と横浜市の境を縦断する尾根道の南側の最終地点となっています。頂上部から西側に開けた平坦地を望むと、町田市の中心市街地を一望することができ、遠くには、丹沢山塊や富士山まで見渡すことができます。また、斜面地にはコナラ、クヌギ、ヤマザクラなどのかつて薪や炭の材料とした二次林といった貴重なみどりが広い面積で残されています。町田市では、この貴重な自然を将来にわたり保全するため、都市緑地法に基づき特別緑地保全地区として指定いたしました。(中略) 〔 第8号 成瀬 山吹(やまぶき)特別緑地保全地区 〕 名称の「山吹(やまぶき)」は、昔からの地名である「山村(やまむら)」と「吹上(ふきあげ)」の両方の場所にまたがることに由来しています。区域は、南北及び東側に伸びており、町田市と横浜市の境を縦断する尾根道の南側の最終地点となっています。頂上部から西側に開けた平坦地を望むと、町田市の中心市街地を一望することができ、遠くには、丹沢山塊や富士山まで見渡すことができます。また、斜面地にはコナラ、クヌギ、ヤマザクラなどのかつて薪や炭の材料とした二次林といった貴重なみどりが広い面積で残されています。町田市では、この貴重な自然を将来にわたり保全するため、都市緑地法に基づき特別緑地保全地区として指定いたしました。(中略)
指定面積:約 4.5ヘクタール / 所在地:町田市成瀬 5000番 2 ほか地内
指定年月日:2013年(平成25年)1月18日 / 町田市役所 公園緑地課 ☎ 042-722-3111(代)
|